2014年12月09日
14式中型自作テーブルソー 完成!
完成しました!

自分で言うのもなんですが 無茶苦茶イイです、これ!(笑 かなり理想に近いものになりました。
テーブルソーを自作している方は多いですが、ここまでアホみたいに懲りまくったものはナカナカないでしょう。(笑 アルミ材を多用したので質感も高めに仕上がりました。質感ってとても大事だと思います。
14式を作る上で参考にしたのはE-Valueの「ETS-10KN」です。この機械をもっとこうしたら良い、ああしたら良いと考えて設計したのでテーブルソーの基本は押さえていると思う。
今回の「14式中型自作テーブルソー」の特徴は次の7つ。
・1.静音
・2.コンパクト
・3.高精度
・4.強度・剛性
・5.機能性
・6.デザイン性
・7.メンテナンス性
特に「静音」と「コンパクト」は市販品を圧倒的に凌駕することを目指し、製作コンセプトに掲げました。自作した理由もここにあります。
ウチは集合住宅なので室内作業になってしまうため、動作音と本体の大きさを極力小さくする必要があるのです。それで市販のテーブルソーはウチの環境にはあまり好ましくないんですね。とにかく購入したETS-10KNの爆音は我慢できなかった…。
サイズ的にはETS-10KNも許容範囲でしたが、とにかく動作音の大きさは完全にNG。他の市販品にも自分の要求するものをクリアした製品が皆無なんですね。音の大きい電動工具は使う気を萎えさせます。ETS-10KNもそれで使用頻度が激減しました。
強いて言えば小型のプロクソンのスーパーサーキュラソウテーブル No.28070 になりますが、テーブルの狭さは完全にアウト。テーブル拡張工事をしたミニサーキュラソウテーブル改(初号機)のように改造が絶対に必要となります。
結局、後日スーパーサーキュラソウテーブル No.28070 買っちゃいました。(つい衝動買い…苦笑
→プロクソン スーパーサーキュラソウテーブル NO.28070 大改修計画(2016.4.11)
どうせ改造をするなら自由に設計できるものをはじめから作った方が何かと都合が良い。ということで中型自作テーブルソー計画を発動しました。
・パワーユニット
パワーユニットにはリョービの丸ノコ「MW-46」をチョイス。決め手はローパワー、安価、コンパクトの3点。とにかく動作音を小さくしたかったので丸ノコとしては最弱と思われる550Wのコイツが最適と判断。また、チップソーは直径が大きくなるほど騒音が大きくなるので小さい147mmのMW-46は好都合。価格もあまり高価だと改造に使うのはもったいない気もしますからね。
最大切断厚は36mmを予定。数値的に大きくありませんが、大物を切ることは滅多にないのでこれで十分。(結果的に最大切断厚は39mmを確保。SPF 2×4材が一発で切れます。)

【リョービ MW-46】
・傾斜切断0~45°
・長さ243×幅205×高さ213(162)mm
( )内のサイズはハンドルから定盤までの高さを表します。
・ノコ刃外径:147mm チップソー
・切込深さ:90°=46mm/45°=30mm
・回転数:3,700min-1
・単相100V・5.7A・550W・2.1kg
・減音工作
密閉に近いボディにパワーユニットを納めることで音漏れを低減させ、さらにボディ内部に吸音材(段ボール)を取り付けることで静粛性を高めました。

段ボールの小さい穴が音を分散させ反射を抑える…はず
以上の構造によって動作音は掃除機の「弱」レベルを実現。テーブルソーとしてはとても静かなものと言えるでしょう。14式を体感してしまった後ではうるさい市販品には二度と戻れない。
視覚的なイメージにするとこんな感じ。

動作音の小ささは感動もの
あとは騒音に付随する問題として振動があります。ETS-10KNのように1,400W級モーターに255mmのチップソーを付けて4,000回転以上でブン回せばそれなりの振動が発生します。この振動対策としてはやはりモーターパワーを下げ、チップソーを直径の小さい物にし、回転数を下げ、ボディ重量を上げることが有効。14式は実用性を維持しながら振動もほとんど気にならないレベルまで低減させました。
直径の大きいチップソーは深切りができる反面、振動を発生させやすくし、遠心力も大きくなるため刃の回転停止に時間がかかるデメリットがあります。
タンスやテーブルといった大型の家具を作る目的ではなく、みかん箱程度の小型工作物を作るのに適したものを想定して設計しました。
■設計
今回のような凝ったものを作るには事前にしっかりした設計図を描いておく必要があります。特に精度が命の工具ならなおさら。それと重要なのは「想像力」ですか。いくらいい道具や技術を持っていても形を想像できなければ何も作ることはできません。
今回もアドビのIllustratorを使って設計。実用性を持った上で極力コンパクトになるようサイズを決めていきます。CADソフトがいい加減欲しいなぁ。
まず、テーブルの基準サイズを W400×D500 くらいに設定。これに左右拡張テーブルを展開させます。使わないときはコンパクトになるようにとの考え。高さは傾斜45°切りが出来るギリギリのサイズ。ゴム足分を含めてテーブル高210mm(ノコ刃、安全カードの突起物除く)。
なお、14式は作業台(事務机)に置いて使用するので脚は付きません。脚まで付けるとしまうとき邪魔くさいですからね。

市販品に比べ断然コンパクトなボディサイズを実現。しかし拡張テーブルを展開させると市販品を上回るテーブル面積になり作業性で劣ることはない。
■市販品とのテーブルサイズ比較
精度にはとことん気を遣いました。精度が狂っていたらすべてが台無しですからね。特に精度が求められるのは天板のレールをノコ刃と並行にセットするところ。誤差は0.05mm以下に抑えられたと思う。
各ガイドの精度も重要。直角・水平、ガタに注意して製作します。
・工具
あとは隙間が出ないように設計通りの寸法で切ったり穴を空けたりする作業。正確に、キレイにアルミをカットできる日立工機のスライド丸ノコ「C6RSHC」は素晴らしい。コイツがなかったら精度が確実にワンランクダウンしたことでしょう。
天板のアルミ板を固定するネジの穴を空けるために神沢鉄工株式会社のドリルガイド「K-801 」を新たに投入。コイツを使うことで穴を垂直に掘ることが出来る。
いい工具はいい仕事をする。
■ボディ
ボディには自作塗装ブースにも使ったMDFボードを採用。MDFボードは加工がしやすいのが良い。
天板に12mm厚、両サイドに18mm厚、背面に9mm厚のMDFボードを配置。重量のかかる丸ノコを支える箇所には18mmと12mmのフィンを設置して強度を確保。人が乗って踊っても大丈夫だと思う。
あえて言おう。強度・剛性のない工具はカスであると!
MDFボード同士の接着は普通の木工用ボンドを使用。これで問題はないとは思いますが、念のためにφ8mmのダボを打ち込みました。

■丸ノコの固定
12mm厚の天板MDFボードに丸ノコのベースがピッタリ合う穴を空けてハメ込みます。その上にアルミ複合板をかぶせ、ドリルでベース諸共穴を空けネジ留め。これで完全にガタが出ません。さらにアルミアングル材を使ってMDFボードとも固定し強度を高めます。

電動工具において強度は安全性に直結する重要な要素なので確実に強固な作りにする
刃を45°にしての傾斜切りや昇降もできる構造にしています。90°オンリーのテーブルソーを自作している人も多いですが、45°傾斜切りは出来た方が絶対便利。溝掘り工作は刃の昇降が不可欠。
■天板
天板は12mm厚のMDFボードの上に3mm厚アルミ複合板、3mm厚アルミ板、2mm厚アルミ板を重ね、層構造にすることでガイド用のレールを作り出します。なお、上層のアルミ板は木材よりも摩擦係数が小さく、強度・耐久性も高いのでテーブルソーの天板に最適。木材と木材ってかなり摩擦抵抗ありますからね。特に湿度の高い日なんて全然滑らなくなる。

アルミ板は質感を高くする効果もあります。
目盛りはパソコンで作ってレーザープリンタで出力。それをラミネート加工して両面テープで貼り付けます。目盛りの線は10、5mm単位を若干太く、長くすることで目盛り合わせをしやすくしました。また、数字を白抜きにして精悍さを演出。
■拡張テーブル
14式の大きな特徴が拡張テーブル。使わないときや小さい物をカットするときは大きなテーブルは不要。必要なときだけ展開できる優れもの。展開に工具は一切不要。

・レフトサイドテーブル
左テーブルは折りたたみ式ですぐ展開可能。切り込みは運搬しやすいよう手が入れられるように。


折りたたみアームが機械ちっくでちょっとカッコイイ。
・ライトサイドテーブル
右テーブルは取り外し式。引っかけて固定パイプを差し込み設置します。取り外し式にしたのは刃の交換や掃除機との接続、電源コードのため。


・バックテーブル
後方テーブルは回転式。持ち上げてネジで固定します。長い部材をカットする場合に部材がテーブルから落ちないようにする。部材が引っ掛からないように本体のテーブルより3mm低く設定。あればちょっと便利かな〜と軽い気持ちで付けたので強度は全然ありません。オマケ工作(笑

バックテーブル展開時でも平行定規が使える設計。オマケ工作ながら結構便利。

・延長テーブル
ミニサーキュラソウテーブル改で製作した拡張テーブルの進化バージョン。拡張テーブルからさらに450mmも延長、840mmまでセットできる。なおかつコンパクトながら目盛り機能も有する優れもの。オマケに左右兼用と至れり尽くせり。コイツは特許を取っておきたい気分。

長い接続パイプを使えばさらなる延長が可能

折りたたみ式で使わないときはコンパクト。接続パイプも収納できます。無論、工具不要。
■ガイド
14式中型自作テーブルソーは4ガイドレールシステムを採用。ガイドは2レール仕様なので1レールに比べ安定した送りができる。
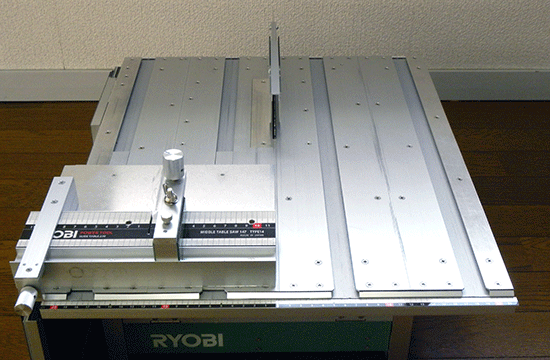
左右、中央にセッティング可能
用意したガイド類は次の4種。
・平行定規(リップフェンス)
20mm等辺角パイプを用いたガイド。テコの原理を応用したハンドル圧力固定方式を採用。 我ながらナカナカ格好良くできました。肉抜き加工を施した柄がカッチョイイ。

本体との一体感を出すために柄の一部をグリーンに塗装。固定はハンドルを押し下げるだけ。木材だとここまでコンパクトには作れません。
・角度切りガイド(マイターゲージ)
自由に角度を設定できる設計。2レール構造なので高い安定感を実現。しかもバイスまで付いているのでズレることがなく精度の高い切断が可能。

0°〜45°まで自由な角度に設定可能


ハーフテーブル仕様の45°専用アダプターを用意
・スライドテーブル
ミニサーキュラソウテーブル改(初号機)で採用したものとほぼ同じ。ノコ刃の切断線上を押し込むことができるので力が偏ることなくキレイな切断が可能。2レール構造。目盛り、ストッパー、ミニバイス付き。

小さい物のカットに便利。ミニバイスは移動可能。
・45°専用スライドテーブル
45°傾斜切断用のスライドテーブル。2レール構造。固定ミニバイス付き。

45°傾斜切断時は安全ガードを撤去
■フロントスペース
14式を設計する上で考慮した一つがフロントスペース。刃の前のテーブル空間です。ここが狭いと長い部材を置くことができず作業性が著しく低下します。

このスペースが作業性に大きく影響する
ETS-10KNはわずか130mmしかありません。市販品で最も奥行きのあるマキタの2703でも170mm。それらに対して14式は265mmを確保。ちょっと長い部材にも補助テーブルを使用することなく切断作業が行えます。147mmのチップソーは深切りはできませんが、フロントスベースを確保しやすいメリットがある。
■チップソー
丸ノコ(MW-46)に標準装備のチップソーは安物の木工用なのでアルミ材もカット可能なリョービの「6653517」 に換装。レーザースリット入りで低騒音・低振動。アルミ材も切れると工作の幅がグッと広がります。
に換装。レーザースリット入りで低騒音・低振動。アルミ材も切れると工作の幅がグッと広がります。

このチップソーはSC-520用ですが、本機でも問題なく使用可能。丸ノコ本体に匹敵するお値段…
■安全対策
テーブルソーは非常に危険な電動工具です。一瞬の不注意で指を切り飛ばすこともあるデンジャラスツール。ETS-10KNで親指を削った経験があるので安全対策は必須事項と心得る。慣れた頃が一番危ない。基本は安全カバーの設置ですね。
・安全カバーと割刃

つまみネジで簡単に取り外し可能
メーカー品も安全カバーには重点を置いていますが、ちょっとカバーが大げさすぎて切断状況が目視しにくい。細かい切断をする場合はカバーが邪魔に感じてしまいます。それでカバーを持ち上げたまま切断作業をしたら刃に指が触れて削れました。
以上のことから、カバーは必須だけど野暮ったいものはダメ。そういうことで幅13mmのスリムデザインに仕上げました。透明度の高い透明アクリル板を使ったので刃の状況が一目瞭然。カバーの先端は刃が少しだけ露出するようにして切断材の切り口と合わせやすくしている。
安全カバーは割刃に装着。割刃はキックバック防止の働きがあります。キックバックとは切断材が刃の回転に巻き込まれて高速でフッ飛んでくる現象です。先が尖っていれば身体に突き刺さるし、重いものだったら内蔵を破裂させることもある。死亡事故も実際に起こっています。目の前にいきなりピッチングマシーンが現れるようなものですね。
14式はETS-10KNに比べローパワーで刃の直径も小さいのでキックバックを起こしたとしても破壊力は比較的小さいといえるでしょう。むやみにパワーがあればいいというものじゃありません。ま、それでもキックバックを起こさないように慎重に作業する必要はあるけどね。
・スイッチ
本機には主電源スイッチとモータースイッチの2つが付いています。主電源スイッチをONにしないとモータースイッチをONにしても動きません。主電源スイッチとモータースイッチは右と左に配置して、左右どちらか空いた片手でスイッチOFFすることが可能なので素早く刃を止めることができます。

左からモータースイッチ、パイロットランプ、内部LEDライトスイッチ、主電源スイッチ
ちなみに、内部LEDライトをONにさせるとモーターへの電源供給が遮断される設計にしています。内部をいじっているときにモーターが回り出すと危険ですからね。安全第一。
・フットスイッチ
本体のスイッチとは別にフットスイッチを用意。琴線に触れるようなものが市販品に存在しなかったので自作しました。電気ブレーキを作動させられるように配線は3芯。4芯仕様のUSBケーブルを流用しました。

両手が塞がった場面でも素早くON/OFFできるので安全・便利! 主電源スイッチをONにしないと作動しない安全設計。サイズはコンパクトカメラほど。使わないときは本体の収納ボックスに収めることができます。テーブルソー使いにとってコイツは本当に感動アイテムですよ。

フルアルミ構造で質感バッチリ。立ち作業での操作なので傾斜を持たせずフラットなデザインにしました。
■切り屑対策
切り屑はほとんど筐体内部に落ちます。筐体の底は引き出しになっているので切り屑を簡単に取り出すことができる。

ダストボックス
また、掃除機接続パイプを標準装備しているので掃除機で吸い込むこともできます。もっとも有効な位置に取り付けたので効果抜群!

ノコ刃のガードに切り屑誘導ガイドを設置して切り屑を接続パイプの方へ導く構造
デザインに拘るのはあららの特徴とも言えるでしょう。カッコイイことは正義です。自作もデザイン性を追求する領域に入りました。


・カラーリング
リョービ製の丸ノコをパワーユニットに採用したということでリョービ製品を模したデザインにしてみました。リョービの電動工具はプロ向け(グリーン配色)とDIY向け(赤配色)のラインナップ分けがされていますが、今回はプロ向けという設定でデザイン。エメラルドグリーン をイメージカラーにしました。
をイメージカラーにしました。
シルバー、エメラルドグリーン、ブラックを基調とした配色でデザイン。
今ではリョービはテーブルソーを国内販売していませんが、かつてはBT3100という製品をリリースしていました。(海外では今でも後継機が売られているみたいです。)そいつはナカナカの高機能で高い人気を誇っていたとか。ただ、いくら高性能でも爆音だったら自分的にはNGですけどね…。

RYOBI BT3100 面白いギミック満載。人気があったことに納得。
・肉抜き加工
カラーリングの他に、肉抜き加工をデザイン要素として取り入れました。まず、前面パネルをパンチング風に加工。ここを肉抜き加工する意味はまったくないのですが、穴を空けた方がいいアクセントになってカッコイイ。(笑

あとは拡張テーブルのベースであるMDFボードを肉抜き加工。これは純粋に軽量化も狙ったもの。ちょっとカッコイイ。MDFボードの地が見えるとちょっとダサいのでフラットブラックで塗装。切り口はアルミ材を貼り付けて質感アップを図る。

平行定規の柄の部分も肉抜き。これは滑り止めの意味もあります。すごい良いアクセントになっていると思う。カッコイイ。

柄の周りには透明アクリル板を接着。アニメのセル画のように裏側にエメラルドグリーン塗装。この処理によっていくら触っても塗装が摩耗で剥げ落ちることがない。見た目も透明感があってキレイ。ダストボックスのフロント部分も同様に処理。よく触る部分だから表面を塗っていたらすぐ禿げてみすぼらしくなってしまう。安全ガードも肉抜き。
・外装
ボディにはMDFボードを使っていますが、これを塗装するのも何なんで今回はアルミ複合板を全面に貼り付けることにしました。この処理でフタもスマートに設置できる。

隙間からMDFボードの地が見えると格好悪いのでブラックを塗っておきます。
ボディの角には貼り合わせ目を隠すため薄いアルミアングル材を接着。しかしただ接着しただけではイマイチなのでコーキング処理を施す。

処理前

処理後
コーキング処理によって一体感がでました。我ながらやることが細かいなぁ。(笑
・ステッカー・デカールチューン
これもあららの自作になくてはならない重要な要素。ロゴ一つ付けるだけでグッと引き締まるんですよ。
ステッカーもアドビのIllustratorで作成。それっぽいデザインにします。データが出来たらアルプス電気のMD-5500を使ってミラーシートのカッティングシートにプリント。ミラーシートを使うことで本物っぽさを演出できます。(笑
プリントしたら表面保護のため極薄のラミネート加工を施し、カッターで切り取ればオリジナルステッカーの出来上がり。

MD-5500は色ズレやカスレが発生しやすいのでちょっと多めに印刷しておきます。
貼り付けたステッカー。うん、本物っぽくて良い感じ。(笑 一体感も醸し出る。

こういうステッカーを貼ると製品っぽくなる(笑


各ガイドには同デザインのステッカーを貼って統一感を出しました

電化製品によく貼ってある銘板ステッカーも制作。それっぽいです。(笑
・ネジ
あとはネジにステンレス製を積極採用。使ったネジの約8割くらいがステンレス。価格は鉄と比べて3倍くらい高くなってしまいますが、質感の誘惑に負けました。(笑 明らかに光沢が違うんですよ。鉄はやっぱり錆びるしナメやすいからね。

ユニクロメッキの鉄製とは明らかに質感が違うステンレスネジ。ネジだけで数千円かかってます。
小ネジの長さカットには電工ペンチを使いました。コイツはネジ山を潰さずに切断できるのです。
刃の交換や角度調整を行うための窓を設けました。どれも開けるのに工具不要。
角度調整のためのフロントパネル。強力磁石による固定なのですぐパカッと開けられます。本体内部の左側には収納ボックスを設置。フットスイッチの収納が可能。

フロントパネルの裏側には45度専用のプレートと工具が取り付けてあります。
刃交換のためのサイドパネル。つまみネジ止め。

刃の交換には5mmの六角レンチを使用
刃昇降のためのリアパネル。つまみネジ止め。

刃の昇降には10mmのスパナを使用
・内部LEDライト
なんと、14式には内部を照らすライトが内蔵されています。テーブルソーでこんな機能を有しているのは世界広しといえどもこの14式くらいでしょう。(笑 刃を傾斜させる時に内部のネジを回す必要があるので取り付けました。

スイッチボックス内部。なんかやたらと複雑(苦笑
・拡張性
レーザーライン設置用の電源ジャック。その気になったらつけるかも。3.3V 2A。

専用台等を作った時に固定するためのネジ穴。φ8mm。

●使用工具
・スライド丸ノコ 日立工機 C6RSHC
・テーブルソー E-Value ETS-10KN
・テーブルソー プロクソン ミニサーキュラソウテーブル28006 改
・卓上ボール盤 レクソン DP2250R
・ドリルドライバ リョービ CDD-1020
・インパクトドライバ リョービ CID-1100
・ドリルガイド 神沢 K-801
・+ドライバー #1、#2
・電工ペンチ
・リベッター
・ピンバイス
・彫刻刀
・鉄工用ノコギリ
・鉄工用ヤスリ
・木工用ヤスリ
・ペーパーヤスリ
・六角レンチ
・レンチ
・ノギス タミヤ 精密ノギス 74030
・木工用ボンド
・万能ボンド ボンド ウルトラ多用途S・U(クリヤー)120ml
・シリコン ボンド シリコンシーラント(ブラック)
・両面テープ
・パソコン Apple Mac Pro
・パソコン Apple iBook G3
・プリンタ ALPS MD-5500
・プリンタ OKIデータ C811dn
・ラミネーター
■総評
一言で言えば、ほんっとに快適!
耳障りな爆音はしないし、アルミ材も木材もスパスパシャープに切れる。フットスイッチでON/OFFもスムーズ。感動すら覚える使用感。我ながらこれは大当たり!
何かを自作する度にクオリティが上がっていきますね。今回の「14式中型自作テーブルソー」は13式自作塗装ブースの3倍手間がかかりました。技術や知識の向上は無論のこと、意識の向上が大きいですね。より良い物を作りたいという欲求。
細かい反省点は多々ありますが、製作コンセプトであった「静音」「コンパクト」はキッチリクリア。完成度も十分満足のいくレベルに仕上がった。テーブルやガイドが充実しているので部材を安定して切断できる。14式のような中型・静音テーブルソーは市販されていないので自分的には非常に貴重なツール。ちなみに、クオリティ重視で作ったので材料費は35,000円くらいかかりました。それでもマキタや日立工機と比べたらお安いですね。仮に受注生産となったら手間がムチャクチャかかってるので製作費は60万円くらいかな。ここまで高いと発注する人なんていないね。
市販品より圧倒的に静音かつパワーも半分以下なので恐怖感もかなり低減。こういうことはスペックに現れないので見落としがちですが、一度体感すると無視できない要素だと気づきます。気軽に使えるって素晴らしい。
電動ノコギリの類は丸ノコ、スライド丸ノコ、14式テーブルソー、ミニサーキュラソウテーブル改、ジグソーの5種も揃いました。何でこんなに揃える必要があるのかと思う方もいるかもしれませんが、それぞれ用途が違うんですよね。
市販品に劣る点は刃の傾斜と昇降が面倒ってところと深切りができない点ですね。それ以外は負けていないと思ってる。プロ向けのスライド丸ノコ・C6RSHCより使い勝手がいいかも。今後の製作活動の中核を担う電動ツールになることは間違いなし。
今回の14式、リョービの人が見たら笑っちゃうでしょうね。リョービの製品カタログに載せてもあまり違和感ないんじゃない?(笑
最後に一言。自作工具の使用は完全に自己責任。設計ミスや工作ミスで重傷を負っても誰も補償してくれません。非常にリスキーなことなのでそれを十分に理解し、安全第一で製作する必要があります。また、作業するに当たっては必ず保護メガネを着用すること。

自分で言うのもなんですが 無茶苦茶イイです、これ!(笑 かなり理想に近いものになりました。
テーブルソーを自作している方は多いですが、ここまでアホみたいに懲りまくったものはナカナカないでしょう。(笑 アルミ材を多用したので質感も高めに仕上がりました。質感ってとても大事だと思います。
14式を作る上で参考にしたのはE-Valueの「ETS-10KN」です。この機械をもっとこうしたら良い、ああしたら良いと考えて設計したのでテーブルソーの基本は押さえていると思う。
| 特徴 |
今回の「14式中型自作テーブルソー」の特徴は次の7つ。
・1.静音
・2.コンパクト
・3.高精度
・4.強度・剛性
・5.機能性
・6.デザイン性
・7.メンテナンス性
特に「静音」と「コンパクト」は市販品を圧倒的に凌駕することを目指し、製作コンセプトに掲げました。自作した理由もここにあります。
| 静音 |
ウチは集合住宅なので室内作業になってしまうため、動作音と本体の大きさを極力小さくする必要があるのです。それで市販のテーブルソーはウチの環境にはあまり好ましくないんですね。とにかく購入したETS-10KNの爆音は我慢できなかった…。
サイズ的にはETS-10KNも許容範囲でしたが、とにかく動作音の大きさは完全にNG。他の市販品にも自分の要求するものをクリアした製品が皆無なんですね。音の大きい電動工具は使う気を萎えさせます。ETS-10KNもそれで使用頻度が激減しました。
強いて言えば小型のプロクソンのスーパーサーキュラソウテーブル No.28070 になりますが、テーブルの狭さは完全にアウト。テーブル拡張工事をしたミニサーキュラソウテーブル改(初号機)のように改造が絶対に必要となります。
結局、後日スーパーサーキュラソウテーブル No.28070 買っちゃいました。(つい衝動買い…苦笑
→プロクソン スーパーサーキュラソウテーブル NO.28070 大改修計画(2016.4.11)
どうせ改造をするなら自由に設計できるものをはじめから作った方が何かと都合が良い。ということで中型自作テーブルソー計画を発動しました。
・パワーユニット
パワーユニットにはリョービの丸ノコ「MW-46」をチョイス。決め手はローパワー、安価、コンパクトの3点。とにかく動作音を小さくしたかったので丸ノコとしては最弱と思われる550Wのコイツが最適と判断。また、チップソーは直径が大きくなるほど騒音が大きくなるので小さい147mmのMW-46は好都合。価格もあまり高価だと改造に使うのはもったいない気もしますからね。
最大切断厚は36mmを予定。数値的に大きくありませんが、大物を切ることは滅多にないのでこれで十分。(結果的に最大切断厚は39mmを確保。SPF 2×4材が一発で切れます。)
【リョービ MW-46】
・傾斜切断0~45°
・長さ243×幅205×高さ213(162)mm
( )内のサイズはハンドルから定盤までの高さを表します。
・ノコ刃外径:147mm チップソー
・切込深さ:90°=46mm/45°=30mm
・回転数:3,700min-1
・単相100V・5.7A・550W・2.1kg
・減音工作
密閉に近いボディにパワーユニットを納めることで音漏れを低減させ、さらにボディ内部に吸音材(段ボール)を取り付けることで静粛性を高めました。
段ボールの小さい穴が音を分散させ反射を抑える…はず
以上の構造によって動作音は掃除機の「弱」レベルを実現。テーブルソーとしてはとても静かなものと言えるでしょう。14式を体感してしまった後ではうるさい市販品には二度と戻れない。
視覚的なイメージにするとこんな感じ。

動作音の小ささは感動もの
あとは騒音に付随する問題として振動があります。ETS-10KNのように1,400W級モーターに255mmのチップソーを付けて4,000回転以上でブン回せばそれなりの振動が発生します。この振動対策としてはやはりモーターパワーを下げ、チップソーを直径の小さい物にし、回転数を下げ、ボディ重量を上げることが有効。14式は実用性を維持しながら振動もほとんど気にならないレベルまで低減させました。
直径の大きいチップソーは深切りができる反面、振動を発生させやすくし、遠心力も大きくなるため刃の回転停止に時間がかかるデメリットがあります。
| コンパクト |
タンスやテーブルといった大型の家具を作る目的ではなく、みかん箱程度の小型工作物を作るのに適したものを想定して設計しました。
■設計
今回のような凝ったものを作るには事前にしっかりした設計図を描いておく必要があります。特に精度が命の工具ならなおさら。それと重要なのは「想像力」ですか。いくらいい道具や技術を持っていても形を想像できなければ何も作ることはできません。
今回もアドビのIllustratorを使って設計。実用性を持った上で極力コンパクトになるようサイズを決めていきます。CADソフトがいい加減欲しいなぁ。
まず、テーブルの基準サイズを W400×D500 くらいに設定。これに左右拡張テーブルを展開させます。使わないときはコンパクトになるようにとの考え。高さは傾斜45°切りが出来るギリギリのサイズ。ゴム足分を含めてテーブル高210mm(ノコ刃、安全カードの突起物除く)。
なお、14式は作業台(事務机)に置いて使用するので脚は付きません。脚まで付けるとしまうとき邪魔くさいですからね。

市販品に比べ断然コンパクトなボディサイズを実現。しかし拡張テーブルを展開させると市販品を上回るテーブル面積になり作業性で劣ることはない。
■市販品とのテーブルサイズ比較
| 14式中型自作テーブルソー | ETS-10KN | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| マキタ 2703 | 日立工機 C 10FE | ||||||||||||||||||
|
|
| 高精度 |
精度にはとことん気を遣いました。精度が狂っていたらすべてが台無しですからね。特に精度が求められるのは天板のレールをノコ刃と並行にセットするところ。誤差は0.05mm以下に抑えられたと思う。
各ガイドの精度も重要。直角・水平、ガタに注意して製作します。
・工具
あとは隙間が出ないように設計通りの寸法で切ったり穴を空けたりする作業。正確に、キレイにアルミをカットできる日立工機のスライド丸ノコ「C6RSHC」は素晴らしい。コイツがなかったら精度が確実にワンランクダウンしたことでしょう。
天板のアルミ板を固定するネジの穴を空けるために神沢鉄工株式会社のドリルガイド「K-801 」を新たに投入。コイツを使うことで穴を垂直に掘ることが出来る。
いい工具はいい仕事をする。
| 強度・剛性 |
■ボディ
ボディには自作塗装ブースにも使ったMDFボードを採用。MDFボードは加工がしやすいのが良い。
天板に12mm厚、両サイドに18mm厚、背面に9mm厚のMDFボードを配置。重量のかかる丸ノコを支える箇所には18mmと12mmのフィンを設置して強度を確保。人が乗って踊っても大丈夫だと思う。
あえて言おう。強度・剛性のない工具はカスであると!
MDFボード同士の接着は普通の木工用ボンドを使用。これで問題はないとは思いますが、念のためにφ8mmのダボを打ち込みました。
■丸ノコの固定
12mm厚の天板MDFボードに丸ノコのベースがピッタリ合う穴を空けてハメ込みます。その上にアルミ複合板をかぶせ、ドリルでベース諸共穴を空けネジ留め。これで完全にガタが出ません。さらにアルミアングル材を使ってMDFボードとも固定し強度を高めます。

電動工具において強度は安全性に直結する重要な要素なので確実に強固な作りにする
刃を45°にしての傾斜切りや昇降もできる構造にしています。90°オンリーのテーブルソーを自作している人も多いですが、45°傾斜切りは出来た方が絶対便利。溝掘り工作は刃の昇降が不可欠。
■天板
天板は12mm厚のMDFボードの上に3mm厚アルミ複合板、3mm厚アルミ板、2mm厚アルミ板を重ね、層構造にすることでガイド用のレールを作り出します。なお、上層のアルミ板は木材よりも摩擦係数が小さく、強度・耐久性も高いのでテーブルソーの天板に最適。木材と木材ってかなり摩擦抵抗ありますからね。特に湿度の高い日なんて全然滑らなくなる。
アルミ板は質感を高くする効果もあります。
目盛りはパソコンで作ってレーザープリンタで出力。それをラミネート加工して両面テープで貼り付けます。目盛りの線は10、5mm単位を若干太く、長くすることで目盛り合わせをしやすくしました。また、数字を白抜きにして精悍さを演出。
| 機能性 |
■拡張テーブル
14式の大きな特徴が拡張テーブル。使わないときや小さい物をカットするときは大きなテーブルは不要。必要なときだけ展開できる優れもの。展開に工具は一切不要。

・レフトサイドテーブル
左テーブルは折りたたみ式ですぐ展開可能。切り込みは運搬しやすいよう手が入れられるように。
折りたたみアームが機械ちっくでちょっとカッコイイ。
・ライトサイドテーブル
右テーブルは取り外し式。引っかけて固定パイプを差し込み設置します。取り外し式にしたのは刃の交換や掃除機との接続、電源コードのため。
・バックテーブル
後方テーブルは回転式。持ち上げてネジで固定します。長い部材をカットする場合に部材がテーブルから落ちないようにする。部材が引っ掛からないように本体のテーブルより3mm低く設定。あればちょっと便利かな〜と軽い気持ちで付けたので強度は全然ありません。オマケ工作(笑
バックテーブル展開時でも平行定規が使える設計。オマケ工作ながら結構便利。
・延長テーブル
ミニサーキュラソウテーブル改で製作した拡張テーブルの進化バージョン。拡張テーブルからさらに450mmも延長、840mmまでセットできる。なおかつコンパクトながら目盛り機能も有する優れもの。オマケに左右兼用と至れり尽くせり。コイツは特許を取っておきたい気分。
長い接続パイプを使えばさらなる延長が可能
折りたたみ式で使わないときはコンパクト。接続パイプも収納できます。無論、工具不要。
■ガイド
14式中型自作テーブルソーは4ガイドレールシステムを採用。ガイドは2レール仕様なので1レールに比べ安定した送りができる。
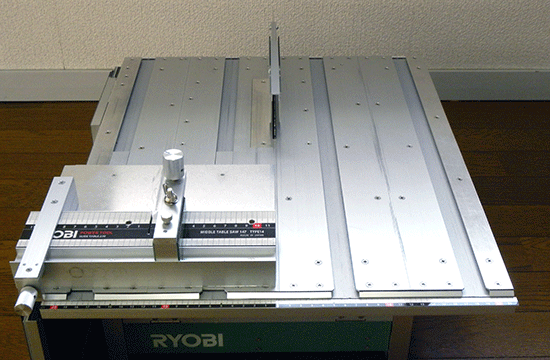
左右、中央にセッティング可能
用意したガイド類は次の4種。
・平行定規(リップフェンス)
20mm等辺角パイプを用いたガイド。テコの原理を応用したハンドル圧力固定方式を採用。 我ながらナカナカ格好良くできました。肉抜き加工を施した柄がカッチョイイ。
本体との一体感を出すために柄の一部をグリーンに塗装。固定はハンドルを押し下げるだけ。木材だとここまでコンパクトには作れません。
・角度切りガイド(マイターゲージ)
自由に角度を設定できる設計。2レール構造なので高い安定感を実現。しかもバイスまで付いているのでズレることがなく精度の高い切断が可能。
0°〜45°まで自由な角度に設定可能
ハーフテーブル仕様の45°専用アダプターを用意
・スライドテーブル
ミニサーキュラソウテーブル改(初号機)で採用したものとほぼ同じ。ノコ刃の切断線上を押し込むことができるので力が偏ることなくキレイな切断が可能。2レール構造。目盛り、ストッパー、ミニバイス付き。
小さい物のカットに便利。ミニバイスは移動可能。
・45°専用スライドテーブル
45°傾斜切断用のスライドテーブル。2レール構造。固定ミニバイス付き。
45°傾斜切断時は安全ガードを撤去
■フロントスペース
14式を設計する上で考慮した一つがフロントスペース。刃の前のテーブル空間です。ここが狭いと長い部材を置くことができず作業性が著しく低下します。

このスペースが作業性に大きく影響する
ETS-10KNはわずか130mmしかありません。市販品で最も奥行きのあるマキタの2703でも170mm。それらに対して14式は265mmを確保。ちょっと長い部材にも補助テーブルを使用することなく切断作業が行えます。147mmのチップソーは深切りはできませんが、フロントスベースを確保しやすいメリットがある。
■チップソー
丸ノコ(MW-46)に標準装備のチップソーは安物の木工用なのでアルミ材もカット可能なリョービの「6653517」
このチップソーはSC-520用ですが、本機でも問題なく使用可能。丸ノコ本体に匹敵するお値段…
■安全対策
テーブルソーは非常に危険な電動工具です。一瞬の不注意で指を切り飛ばすこともあるデンジャラスツール。ETS-10KNで親指を削った経験があるので安全対策は必須事項と心得る。慣れた頃が一番危ない。基本は安全カバーの設置ですね。
・安全カバーと割刃
つまみネジで簡単に取り外し可能
メーカー品も安全カバーには重点を置いていますが、ちょっとカバーが大げさすぎて切断状況が目視しにくい。細かい切断をする場合はカバーが邪魔に感じてしまいます。それでカバーを持ち上げたまま切断作業をしたら刃に指が触れて削れました。
以上のことから、カバーは必須だけど野暮ったいものはダメ。そういうことで幅13mmのスリムデザインに仕上げました。透明度の高い透明アクリル板を使ったので刃の状況が一目瞭然。カバーの先端は刃が少しだけ露出するようにして切断材の切り口と合わせやすくしている。
安全カバーは割刃に装着。割刃はキックバック防止の働きがあります。キックバックとは切断材が刃の回転に巻き込まれて高速でフッ飛んでくる現象です。先が尖っていれば身体に突き刺さるし、重いものだったら内蔵を破裂させることもある。死亡事故も実際に起こっています。目の前にいきなりピッチングマシーンが現れるようなものですね。
14式はETS-10KNに比べローパワーで刃の直径も小さいのでキックバックを起こしたとしても破壊力は比較的小さいといえるでしょう。むやみにパワーがあればいいというものじゃありません。ま、それでもキックバックを起こさないように慎重に作業する必要はあるけどね。
・スイッチ
本機には主電源スイッチとモータースイッチの2つが付いています。主電源スイッチをONにしないとモータースイッチをONにしても動きません。主電源スイッチとモータースイッチは右と左に配置して、左右どちらか空いた片手でスイッチOFFすることが可能なので素早く刃を止めることができます。
左からモータースイッチ、パイロットランプ、内部LEDライトスイッチ、主電源スイッチ
ちなみに、内部LEDライトをONにさせるとモーターへの電源供給が遮断される設計にしています。内部をいじっているときにモーターが回り出すと危険ですからね。安全第一。
・フットスイッチ
本体のスイッチとは別にフットスイッチを用意。琴線に触れるようなものが市販品に存在しなかったので自作しました。電気ブレーキを作動させられるように配線は3芯。4芯仕様のUSBケーブルを流用しました。
両手が塞がった場面でも素早くON/OFFできるので安全・便利! 主電源スイッチをONにしないと作動しない安全設計。サイズはコンパクトカメラほど。使わないときは本体の収納ボックスに収めることができます。テーブルソー使いにとってコイツは本当に感動アイテムですよ。
フルアルミ構造で質感バッチリ。立ち作業での操作なので傾斜を持たせずフラットなデザインにしました。
■切り屑対策
切り屑はほとんど筐体内部に落ちます。筐体の底は引き出しになっているので切り屑を簡単に取り出すことができる。
ダストボックス
また、掃除機接続パイプを標準装備しているので掃除機で吸い込むこともできます。もっとも有効な位置に取り付けたので効果抜群!
ノコ刃のガードに切り屑誘導ガイドを設置して切り屑を接続パイプの方へ導く構造
| デザイン性 |
デザインに拘るのはあららの特徴とも言えるでしょう。カッコイイことは正義です。自作もデザイン性を追求する領域に入りました。


・カラーリング
リョービ製の丸ノコをパワーユニットに採用したということでリョービ製品を模したデザインにしてみました。リョービの電動工具はプロ向け(グリーン配色)とDIY向け(赤配色)のラインナップ分けがされていますが、今回はプロ向けという設定でデザイン。エメラルドグリーン

|  |
| プロ向け W-568D | DIY向け W-1700 |
シルバー、エメラルドグリーン、ブラックを基調とした配色でデザイン。
今ではリョービはテーブルソーを国内販売していませんが、かつてはBT3100という製品をリリースしていました。(海外では今でも後継機が売られているみたいです。)そいつはナカナカの高機能で高い人気を誇っていたとか。ただ、いくら高性能でも爆音だったら自分的にはNGですけどね…。

RYOBI BT3100 面白いギミック満載。人気があったことに納得。
・肉抜き加工
カラーリングの他に、肉抜き加工をデザイン要素として取り入れました。まず、前面パネルをパンチング風に加工。ここを肉抜き加工する意味はまったくないのですが、穴を空けた方がいいアクセントになってカッコイイ。(笑
あとは拡張テーブルのベースであるMDFボードを肉抜き加工。これは純粋に軽量化も狙ったもの。ちょっとカッコイイ。MDFボードの地が見えるとちょっとダサいのでフラットブラックで塗装。切り口はアルミ材を貼り付けて質感アップを図る。
平行定規の柄の部分も肉抜き。これは滑り止めの意味もあります。すごい良いアクセントになっていると思う。カッコイイ。
柄の周りには透明アクリル板を接着。アニメのセル画のように裏側にエメラルドグリーン塗装。この処理によっていくら触っても塗装が摩耗で剥げ落ちることがない。見た目も透明感があってキレイ。ダストボックスのフロント部分も同様に処理。よく触る部分だから表面を塗っていたらすぐ禿げてみすぼらしくなってしまう。安全ガードも肉抜き。
・外装
ボディにはMDFボードを使っていますが、これを塗装するのも何なんで今回はアルミ複合板を全面に貼り付けることにしました。この処理でフタもスマートに設置できる。
隙間からMDFボードの地が見えると格好悪いのでブラックを塗っておきます。
ボディの角には貼り合わせ目を隠すため薄いアルミアングル材を接着。しかしただ接着しただけではイマイチなのでコーキング処理を施す。
処理前
処理後
コーキング処理によって一体感がでました。我ながらやることが細かいなぁ。(笑
・ステッカー・デカールチューン
これもあららの自作になくてはならない重要な要素。ロゴ一つ付けるだけでグッと引き締まるんですよ。
ステッカーもアドビのIllustratorで作成。それっぽいデザインにします。データが出来たらアルプス電気のMD-5500を使ってミラーシートのカッティングシートにプリント。ミラーシートを使うことで本物っぽさを演出できます。(笑
プリントしたら表面保護のため極薄のラミネート加工を施し、カッターで切り取ればオリジナルステッカーの出来上がり。
MD-5500は色ズレやカスレが発生しやすいのでちょっと多めに印刷しておきます。
貼り付けたステッカー。うん、本物っぽくて良い感じ。(笑 一体感も醸し出る。
こういうステッカーを貼ると製品っぽくなる(笑
各ガイドには同デザインのステッカーを貼って統一感を出しました
電化製品によく貼ってある銘板ステッカーも制作。それっぽいです。(笑
・ネジ
あとはネジにステンレス製を積極採用。使ったネジの約8割くらいがステンレス。価格は鉄と比べて3倍くらい高くなってしまいますが、質感の誘惑に負けました。(笑 明らかに光沢が違うんですよ。鉄はやっぱり錆びるしナメやすいからね。
ユニクロメッキの鉄製とは明らかに質感が違うステンレスネジ。ネジだけで数千円かかってます。
小ネジの長さカットには電工ペンチを使いました。コイツはネジ山を潰さずに切断できるのです。
| メンテナンス性 |
刃の交換や角度調整を行うための窓を設けました。どれも開けるのに工具不要。
角度調整のためのフロントパネル。強力磁石による固定なのですぐパカッと開けられます。本体内部の左側には収納ボックスを設置。フットスイッチの収納が可能。
フロントパネルの裏側には45度専用のプレートと工具が取り付けてあります。
刃交換のためのサイドパネル。つまみネジ止め。
刃の交換には5mmの六角レンチを使用
刃昇降のためのリアパネル。つまみネジ止め。
刃の昇降には10mmのスパナを使用
・内部LEDライト
なんと、14式には内部を照らすライトが内蔵されています。テーブルソーでこんな機能を有しているのは世界広しといえどもこの14式くらいでしょう。(笑 刃を傾斜させる時に内部のネジを回す必要があるので取り付けました。
スイッチボックス内部。なんかやたらと複雑(苦笑
・拡張性
レーザーライン設置用の電源ジャック。その気になったらつけるかも。3.3V 2A。
専用台等を作った時に固定するためのネジ穴。φ8mm。
●機器仕様
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 550W |
| 回転数 | 3,700ˉ¹(回 ⁄ 分) |
| 機体寸法 | W433mmxD515mmxH209mm(突起物除く) 補助テーブル展開時:W810×D661×H209mm |
| 取り付け可能ブレード | φ120~147mm |
| ブレードの角度調節 | 90~45度 |
| ブレードの高さ調節 | 0~39mm(φ147mmブレード 90°時) |
| 切断厚さ | 刃傾斜90°:39mm 刃傾斜45°:23mm |
| 重量 | 約22kg |
| 定格使用時間 | 15分 |
●使用工具
・スライド丸ノコ 日立工機 C6RSHC
・テーブルソー E-Value ETS-10KN
・テーブルソー プロクソン ミニサーキュラソウテーブル28006 改
・卓上ボール盤 レクソン DP2250R
・ドリルドライバ リョービ CDD-1020
・インパクトドライバ リョービ CID-1100
・ドリルガイド 神沢 K-801
・+ドライバー #1、#2
・電工ペンチ
・リベッター
・ピンバイス
・彫刻刀
・鉄工用ノコギリ
・鉄工用ヤスリ
・木工用ヤスリ
・ペーパーヤスリ
・六角レンチ
・レンチ
・ノギス タミヤ 精密ノギス 74030
・木工用ボンド
・万能ボンド ボンド ウルトラ多用途S・U(クリヤー)120ml
・シリコン ボンド シリコンシーラント(ブラック)
・両面テープ
・パソコン Apple Mac Pro
・パソコン Apple iBook G3
・プリンタ ALPS MD-5500
・プリンタ OKIデータ C811dn
・ラミネーター
●市販品との比較
| 製品 | 定価 実売 | モーター | サイズ | 重量 | ノコ刃(内径) 最大切り込み深さ |
あらら 14式中型 | 非売品 | 550W 3,700min-1 | W430(810) D500(640) H207 | 22kg | 147mm(20) 90°…39mm 45°…23mm |
E-ValueETS-10KN | オープン 18,034 | 1430W 4,200min-1 | W660 D410 H410 | 25kg | 255mm(25.4) 90°…75mm 45°…63mm |
| マキタ 2703  | 77,144 57,798 | 1430W 4,600min-1 | W686 D560 H458 | 18kg | 255mm(25.4) 90°…91mm 45°…63mm |
マキタ2711
| 140,000 98,000 | 1350W 3,800min-1 | W1090 D715 H407 | 32.5kg | 255mm(25.4) 90°…91mm 45°…63mm |
| 日立工機 C 10FE  | 80,700 69,730 | 1330W 5,000min | W494(864) D535 H310 | 25.4kg | 255mm(25.4) 90°…70mm 45°…55mm |
EvolutionFURY5 | 34,800 31,800 | 1500W 2,500min-1 | W444(812) D625 | 25kg | 255mm(25.4) 90°…73mm 45°…54mm |
PAOCKTBS-255PA | 35,750 18,999 | 1400W 5,000min-1 | W660 D415 | 18.3kg | 255mm(15.9) 90°…76mm 45°…63mm |
プロクソンNo.28070 | 62,000 32,424 | 200W 3,500〜6,000min | W300 D260 H170 | 5.8kg | 85mm(10) 90°…26mm 45°…19mm |
プロクソンNo.27006 | 19,000 11,170 | 80W 3,500min | W247 D186 H124 | 2kg | 50mm(10) 90°…8mm 45°…ーmm |
■総評
一言で言えば、ほんっとに快適!
耳障りな爆音はしないし、アルミ材も木材もスパスパシャープに切れる。フットスイッチでON/OFFもスムーズ。感動すら覚える使用感。我ながらこれは大当たり!
何かを自作する度にクオリティが上がっていきますね。今回の「14式中型自作テーブルソー」は13式自作塗装ブースの3倍手間がかかりました。技術や知識の向上は無論のこと、意識の向上が大きいですね。より良い物を作りたいという欲求。
細かい反省点は多々ありますが、製作コンセプトであった「静音」「コンパクト」はキッチリクリア。完成度も十分満足のいくレベルに仕上がった。テーブルやガイドが充実しているので部材を安定して切断できる。14式のような中型・静音テーブルソーは市販されていないので自分的には非常に貴重なツール。ちなみに、クオリティ重視で作ったので材料費は35,000円くらいかかりました。それでもマキタや日立工機と比べたらお安いですね。仮に受注生産となったら手間がムチャクチャかかってるので製作費は60万円くらいかな。ここまで高いと発注する人なんていないね。
市販品より圧倒的に静音かつパワーも半分以下なので恐怖感もかなり低減。こういうことはスペックに現れないので見落としがちですが、一度体感すると無視できない要素だと気づきます。気軽に使えるって素晴らしい。
電動ノコギリの類は丸ノコ、スライド丸ノコ、14式テーブルソー、ミニサーキュラソウテーブル改、ジグソーの5種も揃いました。何でこんなに揃える必要があるのかと思う方もいるかもしれませんが、それぞれ用途が違うんですよね。
| 特徴 | |
 | ・丸ノコ(日立工機 FC5MA)満足度:★★★ーー 大きい板の切断にしか使わない。キレイに切るにはある程度の経験が必要。小さい物は切れない。精度はそこそこ。木工用。厚さ46mm。 |
 | ・スライド丸ノコ(日立工機 C6RSHC)満足度:★★★★★ 棒状の部材切断に最適。アルミも簡単にキレイに高精度切断。板は幅312mmまで。使用頻度多。アルミ、木工、他。厚さ55mm。 |
 | ・テーブルソー(14式中型自作テーブルソー)満足度:★★★★★ 板状の部材切断に最適。斜め切り、45°切が容易。幅800mmくらいまでの板に対応。高精度切断。使用頻度多。アルミ、木工、他。厚さ39mm。 |
 | ・ミニサーキュラソウテーブル改(プロクソン No.28006)満足度:★★★★ー 薄い板状の精密切断に最適。特にアルミ複合板の切断は秀逸。使用頻度多。アルミ材は切れないことないが、切断面が粗い。プラ板、アルミ複合板。厚さ9mm。 |
 | ・ジグソー(リョービ J-6500VDL)満足度:★★ーーー 曲線切りに特化。直線切り不可。ほとんど出番はない。木工用。厚さ65mm。 |
市販品に劣る点は刃の傾斜と昇降が面倒ってところと深切りができない点ですね。それ以外は負けていないと思ってる。プロ向けのスライド丸ノコ・C6RSHCより使い勝手がいいかも。今後の製作活動の中核を担う電動ツールになることは間違いなし。
今回の14式、リョービの人が見たら笑っちゃうでしょうね。リョービの製品カタログに載せてもあまり違和感ないんじゃない?(笑
最後に一言。自作工具の使用は完全に自己責任。設計ミスや工作ミスで重傷を負っても誰も補償してくれません。非常にリスキーなことなのでそれを十分に理解し、安全第一で製作する必要があります。また、作業するに当たっては必ず保護メガネを着用すること。
◎コメントは内容確認後に掲載となります。なお、責任持てないので技術的質問には原則応じていません。







この記事へのコメント
私は、静音性を高める為に、秋月電子のトライアック調光器キットが使えるとの情報をしり、昨日、それを作りました。あららさんの段ボールでの防音対策、参考になります。フットスイッチは、足を踏んである間だけ電源が入り、足を離したら電源が切れるのが安全だと思いますが、パナソニックなどの市販されているものは、違うようなので、私も自作を考えています。
あららさんのブログ、大変参考になりました。
まさにいい意味でのマニアですね。
私もこんな風に製作出来たらと思います。
使ってもよし、見た目もよし、存在感のある電動工具は最高です。
参考にさせて頂きます。
お褒めいただき恐縮です。
これからもニヤリとさせるようなものを作っていこうと思うのでご期待ください。(笑
RYOBIの新商品だ! と思い込むほどの完成度。
何度も見入っています。是非作ってみたいとの衝動にかられ詳細については想像しながら取り組んで完成品を妄想しながら作成していきます。 素晴らしい記事をありがとうございました。
関心を持って頂きありがとうです。
現在プロクソンのスーパーサーキュラソウテーブル大改造計画を進行中。こっちは改造マニュアルを作って無償配布しようかなと考えています。
自作の方、頑張ってください!
お世話になっております。
先日頂いた設計図を基にサイズや部品調達をやり始め楽しみながら取り組んでおります。
教えていただきたいても宜しいでしょうか?
回路図にある黄色部品は、MW-46取っ手内部のものなのでしょうか?
各LEDに抵抗値と62Ωと記載されているのは別々の値なのでしょうか?
お忙しい中、恐縮ですがご教授ください。
よろしくお願いいたします。
コメありがとうございます。DIYは楽しいですよねー。
本日新記事をアップしました。今回は自作ではなく既製品のボール盤改修作業ですが、結構ナカナカ面白い内容ではないかと思います。ニヤッとしていただければ幸いです。(笑
リョービのテーブルソーを元に改造したのかと、ずっと勘違いしておりました。
一から自作で精度と剛性をだすのは本当に大変だったでしょう。
よーし!これを参考に・・・と思いましたが私が真似したら直角なんて出せるはずもなく、ゴミ製造機になりそうなので断念しておきます。
本当に感動ものですね!
お疲れ様でした。
いらっしゃいませ〜。
ご指摘の通り精度を出すのにちょっと苦労しました。14式もまぁまぁですが、次新しいのを作ったらもっと面白いものができるのではないかと思います。
ま、テーブルソーはもう揃っているので作る予定はないのですが…(笑
新作も期待しています!
こういった電動工具は組み立てと微調整に時間がかかってしまい受注生産は現実的では無いと思います。
それこそ労力考えたら60万だと思います。
ご存知かもしれませんが、図面(設計図)販売はかなり向いていると思いますよ。
http://paoson.com/downloads/en/
youtubeから導線ひっぱってこんな感じで販売されてます。
このテーブルソーだと欲しい人は多いと思います(私がその一人)笑。
paoson.comというのは知りませんでした。3Dデータだとイメージが掴めやすくていいですね。
一応「あららStore」というサイトで塗装ブースの設計図を販売しています。
14式中型自作テーブルソーの設計図は欲しい方には無償で提供しています。ただ、かなり想像力と推察力が必要なので売れるようなシロモノではありません。(苦笑
企画中の新型塗装ブースは製作のしやすさも考慮した親切設計にして製作マニュアル販売をしてもいいかなと企てています。
よろしくお願いします。
参考になる事が多々あり、次は何を自作するのか、楽しみにしております。1つ教えていただきたいのですが、14式中型自作テーブルソーのリップフェンスの細工はどのようにされてるのですか?
返事お待ちしております
14式のリップフェンスは20mmアルミ角パイプの中に10×15mm不等辺角パイプを入れて、テコの原理を応用したレバーで締め付ける構造になっています。
アイディア的に有効とは思うのですが実際に使ってみて、強度や安定性、セットのしやすさという点で28006改や28070改で製作したパッド付きボルト形式の方が良好ということがわかりました。14式のリップフェンスも時間ができたら作り直そうと思っているので参考にしない方がよいと思います。(苦笑
フライス盤の完成楽しみにしてます。